「幼いお子さん の様子に応じた関わり」は、東日本大震災発生時に記載したものです。この記事は、お子さんに強いストレスがか かった場合の対処方法を年齢段階別に示したもので、このシリーズは、「幼い子ども向け」のものです。災害時以外でも、生かしていくことができると思います。幼い子どもの睡眠の問題では、保護者の関わり方の工夫について、支援者が保護者の相談に乗るのが原則です。
睡眠の問題の状態
「布団に入りたがらない」」「ひとりで寝るのを嫌がる」
「夜中に叫んで目を覚ます」「ぐずぐずいつまでも寝ない」
「ひとりでは寝たがらない」「夜中にすぐ目を覚ます」「大きな叫び声をあげる」
睡眠の問題への関わり
一緒に寝るように勧めます
一緒に寝るのは、自分より幼い子と思っている年齢のお子さんであると、それを恥ずかしく感じるかも知れません。それを恥ずかしがって嫌がるようなときは、「寂しいから一緒に寝てくれないかなぁ」と、大人の方がお願いする形で誘う方が良いと保護者にお伝えするのも一つの方法です。
眠る前の習慣を工夫するようにご家族に促します
布団に入る前に、お子さんが好む儀式「本を読み聞かせる」「お祈りをする」「添い寝をする」などを、毎日続けるようにして、習慣にするように保護者に勧めます。
これまでの生活が変わってしまったので、先の見通しが持てなくなっているのです。眠る前にいつも行うことがあることで、お子さんは、「これからお布団に入るんだ」という見通し、気持ちの準備ができるようになります。
抱っこするように勧めましょう。
(眠る前にむずかったときも、夜中に目を覚ました時も…)
「そばにいるよー」「どこにも行かないよー」「平気だよー」「守ってあげるからね」などと、安心させる言葉をゆったりとした口調で語りかけることを保護者に伝えましょう。ゆったりと、のんびりと、語尾を少し延ばすような感じでの語りが良いように思います。
もう大丈夫、安全だと感じられれば、眠りにつくことができます。
「サイコロジカル・ファーストエイド」は、こころのケガの応急手当の方法です。これは、大規模災害、事故などの直後に提供できる、心理的支援のマニュアルです。災害精神保健に関する、さまざまな領域の専門家の知識と経験、および、たくさんの被災者・被害者の声を集めて、アメリカ国立PTSDセンターと、アメリカ国立子どもトラウマティックストレス・ネットワークが開発したものです。この記事は、それを災害の場面に限定して、一般の支援者向けに書き換えたものです。

【PR】
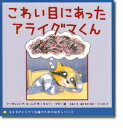 |
こわい目にあったアライグマくん (子どものトラウマ治療のための絵本シリーズ) [ マーガレット・M.ホームズ ] 価格:1,870円 |
マーガレット・ホームズ作、キャリー・ピロー絵(飛鳥井望、亀岡智美監訳、一杉由美訳)
こわい目にあったアライグマくんが、症状に苦しみながらも、治療を受けて立ち直るお話です。











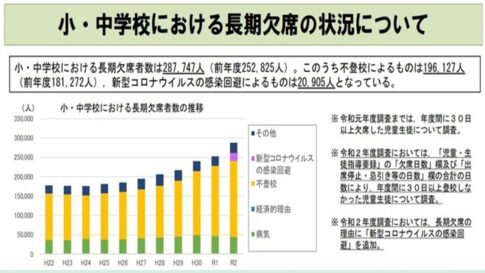

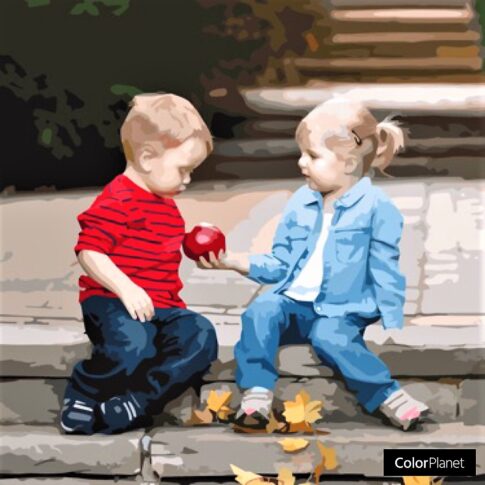

コメントを残す